はじめに
日々を機嫌よく過ごすために、心掛けていることがあります。
それは「不安を減らす」こと。
不安を抱えると、心も表情も曇ってしまいます。でも不安って、なぜか次から次へと出てくるんですよね~。
そんな不安について、「じゃあ、どうしたら減らせるのか」を考え、行動するようにしています。
「言うは易く行うは難し」ですが・・・。
介護は予告なく突然に
今年の初め、パートナーのうにょーさんの親がふとしたことから入院することになりました。
そこから始まる介護問題。
これまで介護を身近に感じることがなかったので、知識や情報がありません!何をどうすればいいのか、右往左往状態でした…。
「介護って、本当にある日いきなり始まるんだ」と実感した出来事です。
その後、いろんな手続きを経て少し落ち着いたのですが、ふと頭をよぎったのが「自分の親は大丈夫だろうか?」ということ。
不安に思ったので、「先手を打とう」と考えました。

父の体の変化から感じた危機感
私の両親は元気に過ごしています。
でも、年齢とともに身体の変化は確実に出てきていると感じますね。
特に父は、背中や腰が曲がり、歩行も以前より困難に。
自力で歩いて移動できる距離が短いため、普段は自転車に乗って移動します。ただそれだと、本人が気を付けて自転車に乗っていても、いつバランスを崩すことがあったり、巻き込まれ事故に会うかわかりません。
そして以前から骨粗しょう症と診断されていると知ったのが、私は今年になってからのこと。
ということは、「もし転んで骨折でもしたら、その瞬間から介護生活が始まるかもしれない」と想像しました。
介護って特別なもの?
「介護なんて、まだ必要ない。」
そう思う方も多いと思います。
多少の病気や、足腰の弱り、軽い認知症など、高齢になればどうしても受け入れざるを得ないことかもしれません。
個人個人、程度の差はあっても、「これくらいで介護なんて」と思いがちな気がします。
だからといって本人や家族が多少我慢すればいい、負担を負えばいい、というものではないと私は思っているんです。
日本には「介護保険制度」というものがあります。
制度の詳細についてここでは触れませんが、40歳以上になると「被保険者」として、みなさん介護保険料を納めています。その保険料で成り立っている制度です。
定められた要件を満たしている方は、その「介護保険」を利用して、日常生活のお手伝いをお願いしたり、家族の負担を軽減するサポートを受けることが可能になります。
身近に利用している方がいないと、なかなかわかりにくい制度かもしれません。私はそういう印象でした。
けれど知ったあとは、「遠慮せず、プロにお願いしてみよう」と思うようになったんです。
介護保険ってすぐ使える?
介護保険制度を利用するには、「申請をする」必要があります。

介護保険を利用したいんだけど…
と所定の申請手続きをして、認定調査を受けます。その結果、
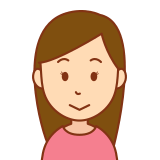
いいですよ
と認めてもらえると利用できるようになります。
申請してから認定結果が出るまで、約1ヶ月以上かかるかもしれません。申請の混雑状況なども影響します。
申請の手順、申請後に受けられるサービスの内容などは、居住地の自治体(市町村役場等)で確認できます。
※介護保険制度は、市町村および特別区(東京23区)が運営しています。そして提供されるサービス内容は、市町村によって異なります。
ということで私は、親が住む自治体の高齢者向けサービスや、介護保険申請について調べました。
そして、受けられるサービスのうち、私目線で必要だと思ったサービスは下記の内容です。
・在宅サービスの訪問リハビリ
・福祉用具のレンタル(歩行器、歩行補助つえなど)
・住宅改修費支給(手すりの取り付け、段差の解消等)
・ケアマネージャーさんによるサポート
・移動支援としてタクシー料金の助成券交付 など
これらは「介護保険の申請」をし、「介護保険」の認定を受けることで利用できます。
ただし、認定結果(要支援1・2、または、要介護1~5いずれか)によって、受けられるサービス内容や自己負担額が変わります。
認定を受けることができれば、ケアマネ-ジャーさんが決まるはずなんですが、その存在は大きい!
「ケアマネ-ジャー=何かあれば相談できる担当者」ができるんです。これは本人だけでなく家族にとっても、安心感につながります。
※ケアマネージャー:介護が必要な人や家族の相談に応じ、ケアプラン作成や関係機関と調整を行ってくれる介護支援専門職の方
介護保険申請のタイミングって?
ただ、介護保険の申請について周りから聞いた話は、
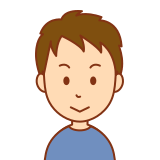
高齢の親が病気で入院したとき、病院側から”介護保険持ってますか?申請してくださいね”と言われてから申請した。
という声が多かったです。
でも、それだと突然すぎて焦ります。パートナーの場合もそうでした。
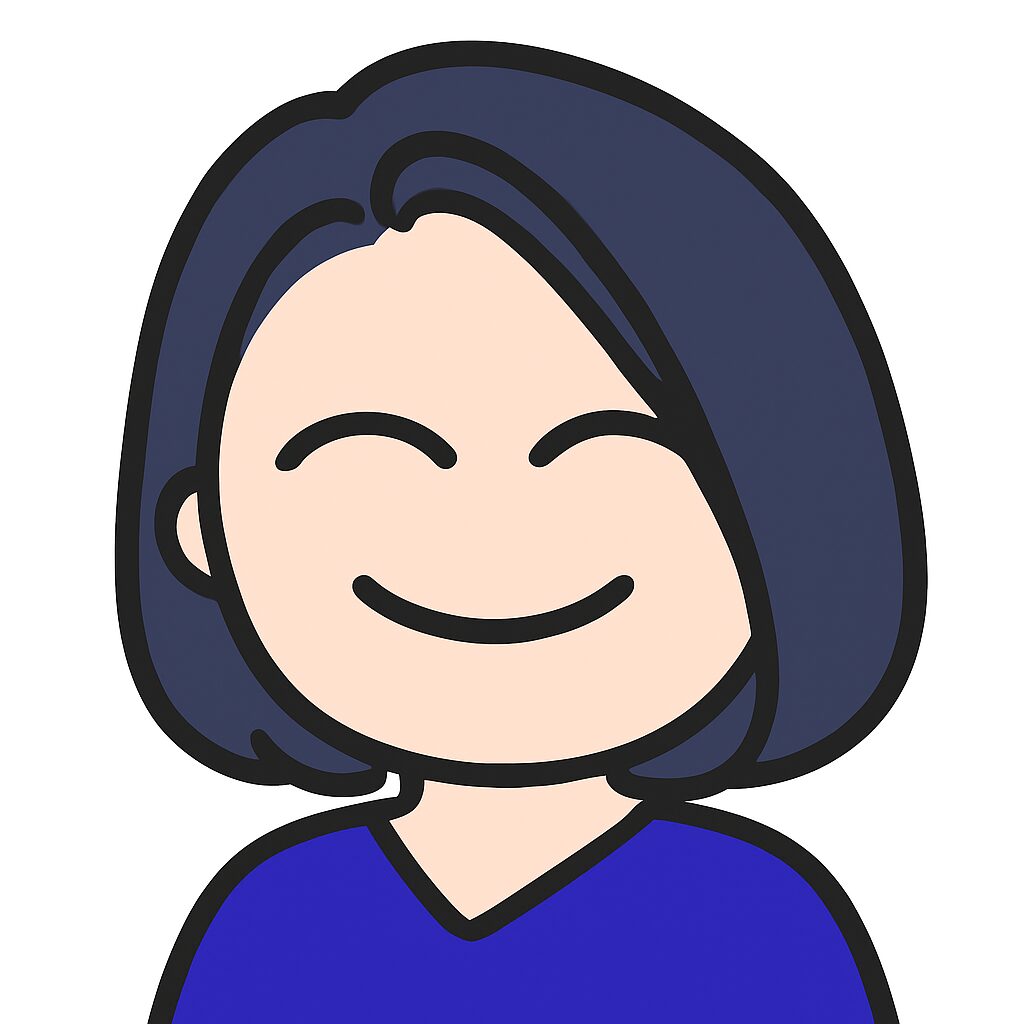
だけど、専門機関から言われてからでないと申請できないんかな?
いえいえ。今回両親の住む自治体の窓口に問い合わせたところ、そうではなかったです。
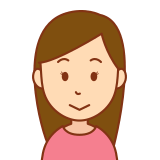
年齢等の要件を満たし、受けたいサービスなどが明確な場合、まずは申請してください。
との返答でした。
「まずは申請」―はい、申請しても却下される場合があるからなんです。
「この人、まだ介護サービスが必要ない状態ですね」と判断されたら、「非該当」という認定結果が届くそうです。
だからこそ、申請してみなければ認定されるかどうかわからない。だったら申請してみよう!―利用者や家族が必要だと思ったら、「介護保険を使いたい」って申請していいんです。
それが最初の一歩になります。
父が受け入れてくれた一歩
ということで「申請しよう」と思ったのですが、果たして当事者である父がどう受け止めるか・・・?
そして他の家族はどう思うだろうか?
現時点では必ずしも必要、という状況ではないため、たとえ良かれと思っても無理強いはできません。
伝え方を間違えれば、父の尊厳を傷つけるかも?など悩み、まずは姉に相談。
そして姉の意見を聞き、同意と協力を得てから、両親に話すことにしました。
結果、ありがたいことに父がすんなりと受け入れてくれましたー!\(^o^)/
「うん。介護保険申請してみる」と。
話してみると、背中や腰の曲がり具合で、周りから「障がい申請は?」など聞かれることもあったそう。
けれど誰も詳しい内容や手続きについては知らず、本人も申請すると何がどういいのかもわからずで、そのまま過ごしていたという話が。
障がいの申請と、介護保険の申請は別物であること。今後必要になるであろう介護保険の申請を、今のうちから検討しないか、という内容で話をしました。
認定を受けることで、父にとってのメリット・デメリットも話し、その結果、父の快諾を得ることができたので、対話って大事ですね~。
というわけでこのあと、申請の準備を進めていくことになるのです。
まとめ:不安は“準備”で減らせる
介護は、誰にとっても「突然」訪れる可能性があります。
パートナーの親の介護に、二人でオロオロした経験を経て、「知識も準備もないままでは怖い」と実感しました。
不安をゼロにするのは難しい。
けれど、心や時間にゆとりがあるうちに、とりあえず介護保険の申請をしておく、相談先を確保しておく、といったことはできます。
そうした準備は不安を減らし、未来の安心につながると思うんです。
今回は私の身内の話ですが、「介護」というのは、どの家庭にも起こり得ることだと思います。
だからこそ「まだ早い」と思ううちに、情報収集だけでも動いておくと、安心を増やす一歩になるかもしれません。
また後日、「介護保険申請編」として、申請に関する具体的な流れをお伝えします。
※この記事内の内容は、サイト管理人が調べたこと・体験したこと、該当機関で確認したことについて書いていますが、管理人の認識不足等により情報についての説明が不十分な点があるかと思います。
介護保険については必ず利用者の方がお住いの自治体でご確認ください。
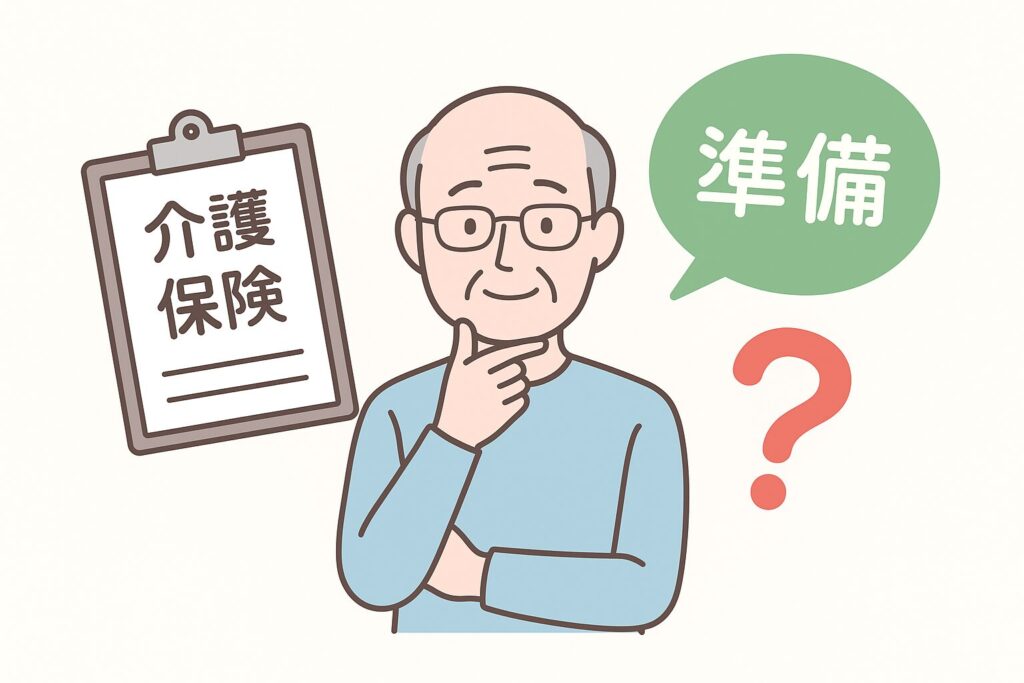
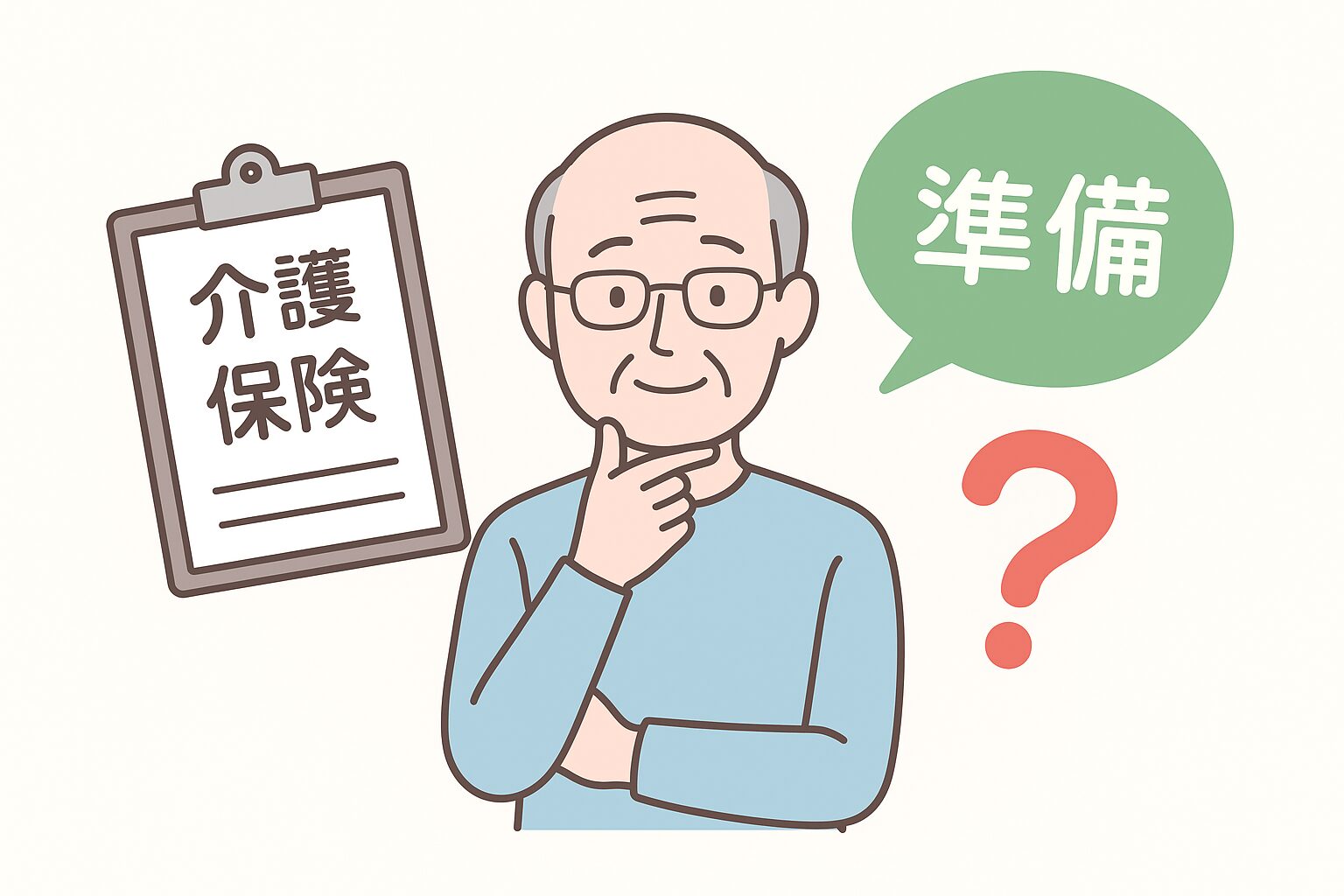
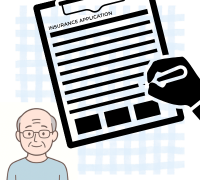
コメント